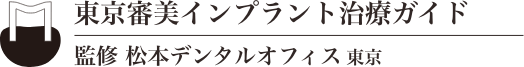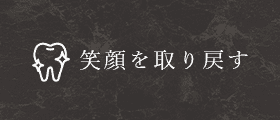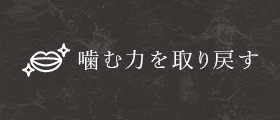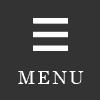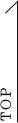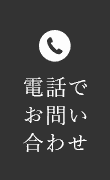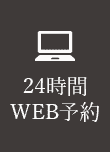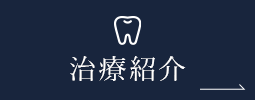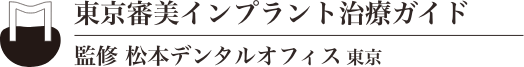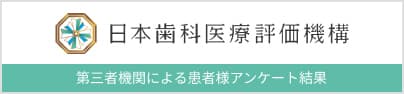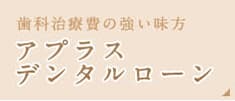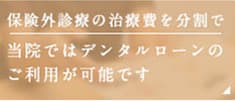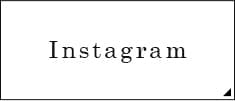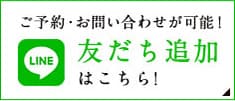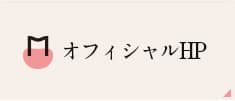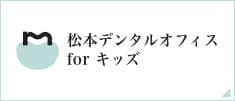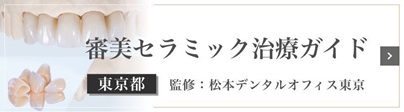1. 「即時埋入インプラント」とは?最初に知っておくべき基本

・抜歯当日に埋め込む治療の定義
即時埋入インプラントとは、むし歯や歯周病などで抜歯が必要になった同じ日にインプラントを埋め込む方法です。
抜歯窩(ばっしか:歯を抜いた穴)の骨が大きく変化する前に支台を確保できるため、治療期間の短縮や歯ぐきの形態維持が期待できます。
ただし、いつでも適用できるわけではなく、感染や腫れが強くないこと・残存骨が十分で初期固定が得られることなどの条件を満たす必要があります。
また、即時埋入は外科処置である以上デメリットやリスク(腫れ・痛み・初期固定不足・審美的退縮の可能性)も伴います。
「早く治したい」気持ちに寄り添いつつも、安全に進められるかどうかの診断が最優先です。
・「即時埋入」と「即時荷重(当日仮歯)」の違い
似た言葉に「即時荷重」があります。これは当日に仮歯を固定して見た目や発音、軽い咬合機能を回復させることを指します。
つまり、当日に埋めるか(即時埋入)と、当日に噛ませるか(即時荷重)は別の判断軸です。
たとえば前歯部では審美性を優先して仮歯を装着する一方、臼歯部や歯ぎしりが強い方では荷重を控えめにするなど、症例に応じたコントロールが必要です。
この区別を理解しておくと、即時埋入インプラントの条件やデメリットの説明も納得しやすくなります。
・どんな人に向く?全体像をつかむ
即時埋入が検討しやすいのは、①抜歯部に急性の感染や膿がない、②抜歯窩の周囲に連続した骨壁が残る、③全身状態(糖代謝・喫煙・服用薬など)が安定している方です。
一方で、感染が強い・骨の欠損が大きい・歯ぐきが非常に薄い・強い咬合癖がある場合は、早期埋入や遅延埋入へ切り替えたほうが安全なこともあります。
メリットは「期間の短縮」「見た目の早期回復」「骨吸収の抑制が期待できる」こと。デメリットは「適応を外れると初期固定が弱い」「歯肉退縮など審美面の不確実性」「感染再燃や二次処置の可能性」です。
当院ではCTや口腔内写真で条件を丁寧に評価し、即時・早期・遅延の選択肢を比較してご説明します。
“最短”より“最適”。まずは現状を可視化し、あなたに合う治療の道筋を一緒に決めていきましょう。
2. 即時埋入インプラントの“条件”①:感染コントロール

・抜歯窩の感染がないことが大前提
即時埋入インプラントを安全に行うためには、まず抜歯部に感染や炎症が残っていないことが絶対条件です。
歯根の先に膿がたまっていたり、急性の歯周病が進行していたりすると、インプラントと骨が結合する過程(オッセオインテグレーション)が阻害される可能性があります。
そのため、松本デンタルオフィス東京では、手術前に歯周ポケットの細菌検査・レントゲン・CTによる骨吸収の確認を行い、感染の有無を詳細に診断します。
炎症がある場合はすぐに埋入せず、まず消毒・抗菌処置を行い、炎症が落ち着いた時点で改めて計画を立て直すのが安全です。
“早く治す”ことよりも“確実に治す”ことを優先するのが、長期的に見て最も良い結果を生みます。
・バイオフィルム除去と術前クリーニングの重要性
抜歯直後の歯根面や歯槽骨の表面には、目に見えない細菌の膜(バイオフィルム)が付着しています。これを残したままインプラントを埋入すると、後にインプラント周囲炎を引き起こすリスクが高まります。
そのため、抜歯と同時に感染組織や肉芽(にくげ)を丁寧に除去し、必要に応じて抗菌剤による洗浄やレーザー殺菌を併用します。
また、手術の数日前に歯石除去や口腔内クリーニングを行うことで、全体の細菌量を減らし、手術後の感染を最小限に抑えることができます。
一見小さな工程に見えても、この“術前準備”が成功率を大きく左右します。
・全身状態と免疫バランスの確認
口腔内だけでなく、全身の健康状態も即時埋入の成功条件に直結します。
糖尿病で血糖コントロールが不十分な方や、免疫抑制剤を使用している方、喫煙習慣のある方では、傷の治りや骨の再生力が低下する傾向があります。
そのため、手術前には血液検査で炎症反応や血糖値を確認し、必要に応じて主治医と連携を取ります。
また、喫煙者の方には少なくとも手術の2週間前から禁煙していただくことで、血流と酸素供給を改善し、感染リスクを下げることができます。
これらの慎重な準備を経て初めて、「即時埋入をしても安全」と判断できるのです。
感染を徹底的にコントロールすること――それが即時埋入インプラント成功の第一条件です。
3. 条件②:骨の量と質・抜歯窩の形

・初期固定を得るための「骨量」と「骨質」
即時埋入インプラントでは、歯を抜いた直後にインプラント体を埋め込むため、まず重要なのが初期固定(しょきこてい)です。
初期固定とは、インプラントを埋入した際にどれだけ安定して固定されるかという指標で、治療の成否を大きく左右します。
具体的には、顎の骨(歯槽骨)の厚み・高さ・密度が十分であることが条件です。
とくに上顎の奥歯では、骨がやわらかく、上顎洞(副鼻腔)までの距離が短いため、慎重な埋入位置の設定が欠かせません。
松本デンタルオフィス東京では、CT撮影による三次元画像解析を行い、骨量や骨質をミクロン単位で確認。必要に応じて、骨補填材やメンブレン(人工膜)を併用し、初期固定の安定を図ります。
この「骨を読む力」と「支える設計力」が、即時埋入の成功率を大きく左右します。
・抜歯窩の形態と残存骨壁の重要性
もうひとつの重要な条件が、抜歯窩(ばっしか)の形と骨壁の連続性です。
歯を抜いたあとの穴の形が整っており、特に唇側(または頬側)の骨壁がしっかり残っていることが、インプラントを正しい位置・角度で固定するための前提条件です。
もし抜歯時に骨壁が欠けてしまった場合、そのまま埋入すると歯肉が下がったり、金属が透けて見えたりする審美的なトラブルが起きることもあります。
そのような場合は、無理に即時埋入を行わず、まず骨再生治療(GBR)を優先することもあります。
「骨のある部分に打ち込む」だけではなく、「骨を守る」「骨を育てる」ことを見据えるのが、現代のインプラント治療の考え方です。
・骨が足りない場合の選択肢
骨量が不十分でも、即時埋入を完全に諦める必要はありません。
現在では、骨補填材や人工骨膜を使った同時骨造成(ソケットプリザベーション)を併用することで、抜歯窩の形を整えながらインプラントを安定させることが可能です。
また、下顎の骨が厚く、骨質の良いエリアを利用する「傾斜埋入」や、上顎洞を避けて埋め込む「サイナスリフト・ソケットリフト」などの応用的手技もあります。
このような選択肢を駆使することで、“骨が少ないからできない”を“骨が少なくてもできる”に変えることができます。
ただし、骨造成を伴う即時埋入は技術的に難易度が高く、経験豊富な歯科医師による慎重な判断と設計が不可欠です。
「骨の状態を正確に見極め、最もリスクの少ない方法を選ぶ」――それが、長期的に安定した結果を得るための基本です。
4. 条件③:軟組織(歯ぐき)と審美リスク

・歯ぐきの厚みが「見た目の安定性」を左右する
即時埋入インプラントでは、抜歯した直後にインプラントを埋め込むため、歯ぐき(軟組織)の厚みと質が非常に重要になります。
歯ぐきが薄い場合、治療後に歯肉が下がりやすく、金属が透けて見えたり、歯と歯の間に黒いすき間(ブラックトライアングル)が生じることがあります。
特に前歯部では、わずかな歯肉の後退でも審美性に大きく影響するため、事前に歯ぐきの厚みやラインを精密に評価します。
松本デンタルオフィス東京では、必要に応じて歯肉移植(結合組織移植)を併用し、厚みを確保することで自然な見た目を再現します。
インプラントの成功は「骨の固定」だけではなく、「歯ぐきの美しさを守れるかどうか」でも決まるのです。
・前歯部で特に注意すべき“審美的リスク”
前歯の即時埋入は、骨や歯ぐきが薄く繊細なため、他の部位よりも難易度が高いとされています。
抜歯によって唇側の骨が失われやすく、埋入位置を誤ると、歯ぐきが下がりインプラントが露出してしまうこともあります。
また、歯肉の高さや歯間乳頭の形態が左右で異なると、不自然な印象になりやすいため、プロビジョナル(仮歯)で歯ぐきを整えるステップが欠かせません。
この段階で歯ぐきの形を慎重にコントロールし、最終的な人工歯(クラウン)を装着した際に自然な仕上がりになるよう設計します。
「見た目も機能も両立するインプラント」を目指すためには、こうした審美的配慮が不可欠です。
・仮歯(プロビジョナル)で歯ぐきを“育てる”
即時埋入の大きな特徴は、抜歯当日に仮歯を装着できるケースがあることです。
これは単に見た目を整えるためだけでなく、歯ぐきのラインやボリュームを調整しながら、理想的な歯肉形態を作り上げていく「プロビジョナリゼーション」という治療プロセスの一部です。
仮歯の形を微調整することで、歯肉が自然なカーブを描き、最終的なセラミッククラウンがより調和の取れた印象に仕上がります。
ただし、初期固定が不十分な場合や骨・歯ぐきの状態が不安定な場合は、仮歯をすぐに固定せず、荷重をかけない期間を設けることもあります。
このように、歯ぐきの厚み・形・位置を時間をかけて整える工程こそが、長期的に安定した審美結果につながるのです。
「歯ぐきのデザインまで考えるインプラント」――それが即時埋入を成功させるための第三の条件です。
5. 条件④:全身状態・生活習慣

・糖尿病・高血圧・骨代謝関連薬の影響
即時埋入インプラントの可否を判断する上で、歯ぐきや骨の状態だけでなく全身の健康状態も極めて重要です。
特に注意が必要なのが糖尿病・高血圧・骨粗しょう症の治療薬などを服用している方です。
糖尿病の方は血糖コントロールが不安定だと傷の治りが遅くなり、感染リスクが高まる傾向にあります。
また、骨粗しょう症治療薬(ビスフォスフォネート系・デノスマブなど)は骨代謝を抑える作用があるため、インプラント埋入部位の骨再生が遅れる場合があります。
これらの薬を使用している場合、投薬期間や休薬の必要性を主治医と連携して確認した上で治療を進めることが重要です。
松本デンタルオフィス東京では、全身管理の観点から術前に採血や問診を行い、安全な条件で即時埋入を行う体制を整えています。
・喫煙習慣と治癒力への影響
喫煙はインプラント治療全般に悪影響を与える要因の一つです。特に即時埋入では、抜歯後すぐにインプラントを固定するため、血流と酸素供給が非常に重要になります。
しかし、ニコチンは血管を収縮させ、酸素供給を妨げるため、インプラントと骨が結合しにくくなります。さらに、歯ぐきの治癒も遅れることで、インプラント周囲炎(炎症)のリスクが上がります。
そのため、手術の2週間前から禁煙を行い、術後も最低1か月は再開を控えることが推奨されます。
禁煙が難しい場合でも、喫煙本数の制限や加熱式たばこへの切り替えなど、歯科医師と相談しながらリスクを最小限にすることが大切です。
「タバコがインプラントの敵」であることを理解し、治療の成功率を自分自身で守る意識が求められます。
・ストレス・睡眠・栄養も成功を左右する
即時埋入インプラントは、身体の自然治癒力を活かす治療法でもあります。
したがって、日常のストレス・睡眠・食生活といった生活習慣が治療結果に影響を与えることも珍しくありません。
強いストレス状態にあると交感神経が優位になり、血流や免疫力が低下します。睡眠不足や過度な飲酒も、回復の妨げになる要因です。
また、たんぱく質・カルシウム・ビタミンCなど、骨や組織の再生に関わる栄養素が不足すると、インプラントの定着が遅れることがあります。
松本デンタルオフィス東京では、手術前後の生活指導にも力を入れており、食事・睡眠・ストレス管理などをトータルでサポートしています。
「インプラントは手術だけで終わりではない」――治療の成功は、患者様ご自身の体調管理と生活習慣の見直しによって大きく左右されるのです。
6. 即時埋入インプラントのデメリットとは?

・失敗リスクが高まるケースがある
即時埋入インプラントは、抜歯と同時にインプラントを埋め込むため、従来法に比べて技術的な難易度が高い治療法です。
抜歯後の骨や歯ぐきの状態が安定していない段階で埋入するため、初期固定が得られにくかったり、角度の微調整が難しい場合もあります。
もし初期固定が不十分なまま仮歯を装着すると、微細な動揺によって骨との結合(オッセオインテグレーション)が妨げられ、インプラントが脱落してしまうリスクもあります。
そのため、松本デンタルオフィス東京では、即時埋入を希望される場合でも骨質・骨量・歯肉・噛み合わせ・全身状態などを慎重に診断し、最も安全な方法を選択しています。
すべての患者様に即時埋入が適しているわけではなく、「できるケース」と「控えたほうがよいケース」の見極めがとても大切です。
・感染のリスクとアフターケアの重要性
抜歯直後は、歯の周囲に炎症や細菌感染のリスクが残っている場合があります。
この状態でインプラントを埋め込むと、感染がインプラント周囲に広がり、インプラント周囲炎を起こす危険性があります。
とくに、歯周病が原因で抜歯した場合や、歯根周囲に膿が溜まっていた症例では、感染コントロールを慎重に行うことが不可欠です。
手術前に抗菌薬で炎症を抑え、抜歯時にも徹底した洗浄・除菌を行うことでリスクを軽減します。
また、治療後の定期的なメンテナンスとセルフケアも成功の鍵です。術後1~2週間は消毒と経過観察のために必ず来院し、3か月以降も定期的なクリーニングを行うことで、長期的な安定が得られます。
・前歯部では審美的トラブルのリスクも
即時埋入のもう一つのデメリットは、審美的なリスクです。
特に前歯部では、骨が薄く歯ぐきも繊細なため、抜歯時に骨壁がわずかに失われるだけで歯肉の位置が下がり、インプラントが透けて見える可能性があります。
また、抜歯直後の歯ぐきはまだ形が安定していないため、治療後に歯肉の高さが変化して左右差が出ることもあります。
これらを防ぐためには、歯ぐきの厚みを確保する処置(結合組織移植)や、仮歯で歯肉の形を整えるプロビジョナル治療が欠かせません。
さらに、即時埋入ではインプラントの位置や角度がわずかにズレると見た目に影響するため、サージカルガイドを用いた精密な埋入シミュレーションが不可欠です。
技術的ハードルは高いものの、こうした手順を踏むことで、自然で美しい仕上がりを実現することが可能です。
7. 即時埋入インプラントが向かないケースとは?

・重度の歯周病や感染がある場合
即時埋入インプラントは、抜歯後の骨や歯ぐきが清潔で安定していることが前提です。
しかし、重度の歯周病や根尖病巣(歯根の先に膿が溜まる状態)がある場合、その感染源が残ったままインプラントを埋め込むと、インプラント周囲炎を引き起こすリスクが高まります。
また、歯槽骨が大きく吸収している場合、インプラントを支える骨量が足りず、初期固定が得られにくいこともあります。
このようなケースでは、まず感染除去と骨造成(GBR)を先に行うことで、後のインプラント成功率を高めることができます。
「すぐに入れる」ことを優先するよりも、「長く安定して使える」環境を整えることが大切です。
・骨が薄い、または骨の形態が複雑な場合
抜歯即時埋入を成功させるには、インプラントを安定させるだけの骨の厚みと高さが必要です。
特に上顎の前歯部や臼歯部では、骨が薄くなっていたり、上顎洞(副鼻腔)や神経が近接していることがあります。
このような場合、無理に即時埋入を行うと、インプラントの先端が上顎洞や神経に接触してしまう危険性があります。
そのため、骨が不足しているときは、骨造成(サイナスリフト・ソケットリフトなど)を併用して、十分な骨量を確保してから埋入するのが安全です。
松本デンタルオフィス東京では、事前のCT撮影で骨の形や厚みを三次元的に分析し、即時埋入が可能かどうかを正確に判断しています。
・強い食いしばりや歯ぎしりの癖がある場合
食いしばりや歯ぎしりの癖がある方は、インプラントに過剰な力(咬合力)がかかりやすく、即時埋入を行うと初期固定に悪影響を与えることがあります。
特に抜歯直後のインプラントはまだ骨と完全に結合していないため、強い圧力が加わると微小な動揺が起き、結合が妨げられる危険性があります。
こうした場合は、一時的に仮歯を外す・夜間用マウスピースを装着するなどの対策を行い、インプラントへの負荷を最小限に抑えます。
また、噛み合わせの強さをデジタル咬合検査で分析し、必要に応じて噛み合わせ調整を行うことで、長期的な安定を確保します。
即時埋入を成功させるには、単に「骨があるかどうか」だけでなく、「噛み合わせのバランス」まで総合的に考えることが重要です。
8. 即時埋入インプラントを成功させるためのポイント

・正確な診断とデジタルプランニング
即時埋入インプラントの成否は、手術そのものよりも事前の診断と設計に大きく左右されます。
松本デンタルオフィス東京では、CTスキャンによる三次元画像をもとに、骨の厚み・高さ・神経や血管の位置を正確に把握します。
さらに、これらのデータをデジタル上で解析し、サージカルガイド(手術用テンプレート)を作成します。
ガイドを使用することで、埋入角度や深さをミクロン単位でコントロールでき、審美的にも機能的にも理想的な位置にインプラントを配置することが可能になります。
「即時埋入=スピード重視の治療」ではなく、精密設計によって成功を導く治療であることが重要です。
・骨と歯ぐきのバランスを整える処置
抜歯直後の状態は、骨の欠損や歯ぐきの厚みが不均一であることが多く、そのままではインプラントの安定が得られません。
そのため、即時埋入では、骨補填材(人工骨)を併用して骨の空隙を埋める、または歯ぐきの厚みを補う軟組織移植などを同時に行う場合があります。
こうした処置により、インプラントの初期固定を高めると同時に、長期的に美しい歯肉ラインを維持することができます。
「抜いてすぐ入れる」だけでなく、「環境を整えて入れる」ことが、即時埋入を安全に成功させるための大前提です。
・経験豊富な歯科医師による判断と技術
即時埋入インプラントは、通常の埋入よりも難易度が高く、埋入位置・角度・初期固定の調整には高度な判断力と経験が必要です。
松本デンタルオフィス東京では、インプラント専門医がCT画像を用いた診断から埋入までを一貫して担当し、骨質や歯ぐきの状態をリアルタイムで確認しながら手術を行っています。
また、術中は静脈内鎮静法(リラックス麻酔)を併用し、患者様の不安や痛みを最小限に抑えることも可能です。
経験豊富な医師による判断が、即時埋入を「安全で確実な治療」として成立させる最大の鍵となります。
「技術×診断×安全管理」、この3つの要素が揃って初めて、真の即時埋入インプラントが実現します。
9. 即時埋入インプラントで得られるメリット

・治療期間の短縮と早期の見た目回復
即時埋入インプラントの最大の魅力は、治療期間を大幅に短縮できることです。
通常のインプラントでは、抜歯後に3〜6か月の治癒期間を設けてから埋入手術を行いますが、即時埋入では抜歯と同日にインプラントを埋め込みます。
さらに、初期固定が得られれば当日に仮歯を装着することも可能で、歯を失った状態で過ごす期間をなくせます。
特に前歯など見た目が気になる部位では、仮歯によって自然な口元をすぐに取り戻せるため、心理的ストレスの軽減にもつながります。
「歯を失ったその日から笑顔を取り戻せる」――それが即時埋入の大きなメリットです。
・骨吸収の抑制と歯ぐきの形態維持
抜歯を行うと、歯を支えていた歯槽骨は時間の経過とともに吸収し、痩せてしまいます。
しかし、抜歯直後にインプラントを埋入すると、骨に刺激が加わることで骨吸収を防ぎやすくなるという利点があります。
また、インプラント体が歯根の代わりとなることで、歯ぐきの形態も維持しやすく、自然な輪郭を保つことができます。
特に審美領域では、歯ぐきのラインを守ることが仕上がりの美しさに直結します。
「時間を待たずに、骨と歯ぐきを守る」――これは即時埋入ならではの生体的メリットです。
・生活の質(QOL)が向上する
即時埋入によって、歯を失った期間の不便さや見た目の悩みが最小限に抑えられるため、食事・会話・表情など日常生活の質(QOL)が向上します。
仮歯でもある程度の咀嚼が可能で、発音にも支障が出にくく、自然な会話を続けられます。
また、早期に咬合を回復できるため、噛み合わせのバランスが崩れにくく、他の歯への負担を軽減できます。
さらに、審美性の高い仮歯を装着することで、治療期間中も自信を持って人前に出ることができるのも大きな利点です。
即時埋入インプラントは、単に「早い治療」ではなく、「患者様の生活そのものを支える治療法」といえるでしょう。
10. まとめ:即時埋入インプラントの条件とデメリットを正しく理解して選択を

・「誰でもできる治療」ではないからこそ、慎重な診断が必要
即時埋入インプラントは、抜歯と同時にインプラントを埋め込むことで治療期間を大幅に短縮できる、非常に魅力的な治療法です。
しかし、その一方で、骨や歯ぐきの状態・感染の有無・噛み合わせ・全身状態など、複数の条件が整っていることが必須です。
これらの要素がそろわないまま無理に手術を行うと、初期固定が得られずに脱落したり、見た目や噛み合わせに問題が生じるリスクがあります。
したがって、「即時埋入が可能かどうか」は、専門的な診断と正確な画像分析によって慎重に判断されるべきなのです。
松本デンタルオフィス東京では、CT画像とデジタルシミュレーションを活用し、患者様一人ひとりに最も安全で確実な治療計画をご提案しています。
・メリットとデメリットのバランスを理解することが成功の鍵
即時埋入には、治療期間の短縮・審美性の維持・骨吸収の抑制といった大きなメリットがありますが、同時に感染リスク・初期固定の不安定性・審美的変化といったデメリットも存在します。
重要なのは、これらをしっかり理解したうえで、患者様ご自身が納得して治療に臨むことです。
「早く治したい」という思いを叶えるためにも、まずは自分の口腔環境や生活習慣が即時埋入に向いているかどうかを知ることが第一歩となります。
無理にスピードを優先せず、“長く快適に使えるインプラント”を目指す視点を持つことが大切です。
・専門性の高い医院で、安全かつ美しい結果を
即時埋入インプラントは、正しい条件のもとで行えば、機能面・審美面ともに非常に優れた結果が得られる治療法です。
ただし、高度な技術と精密な設計を必要とするため、経験豊富なインプラント専門医による施術が不可欠です。
松本デンタルオフィス東京では、豊富な実績と専門的知識をもつドクターが、CT診断・デジタルガイド・静脈内鎮静法などを駆使し、患者様の不安を取り除きながら安全に治療を行っています。
「できるだけ早く歯を取り戻したい」「抜歯と同時にインプラントを入れたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの骨や歯ぐきの状態を丁寧に診断し、最適なタイミングと方法で理想の口元を取り戻すお手伝いをいたします。
『 東京審美インプラント治療ガイド:監修 松本デンタルオフィス東京 』
監修:松本デンタルオフィス東京
所在地:東京都東大和市清原4丁目10−27 M‐ONEビル 2F
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス
院長 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより