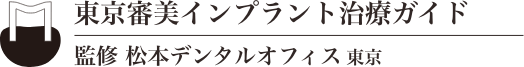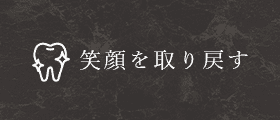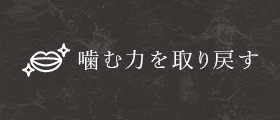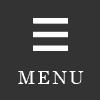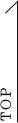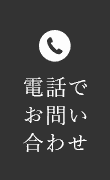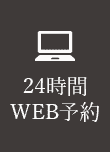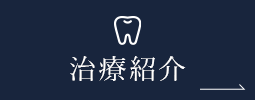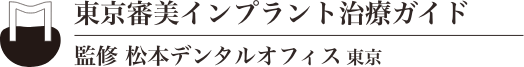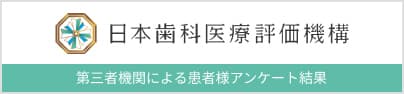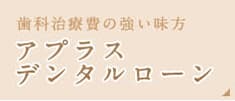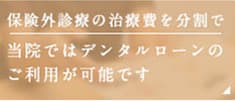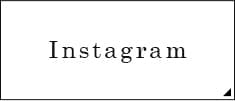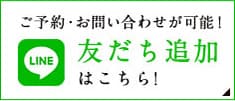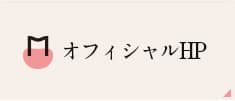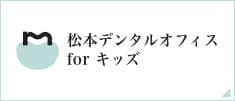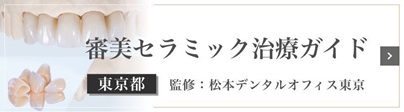1. “もう噛めない”と悩んでいた方が知った、オールオンフォーという選択肢

・「総入れ歯が合わず食事が楽しめない」そんな悩みに気づいた瞬間
総入れ歯を使っている方からよく聞くのが「食事を心から楽しめなくなった」という声です。外れやすい、噛むと痛い、会話中にズレが気になる──こうしたストレスが積み重なると、人前で笑うことさえ控えてしまう方もいます。
毎日の食事は生活の中心にあるものです。にもかかわらず、そのたびに不安を抱えるようになったり、硬いものを避けるようになったりすると、日常の満足度が大きく下がってしまいます。こうした悩みは「歳だから仕方がない」と思われがちですが、実は治療の選択肢はひとつではありません。
その代表がオールオンフォーと呼ばれる治療法です。総入れ歯の不安定さや噛みにくさに悩む方にとって、これまでとはまったく異なる解決策となり得ます。
・オールオンフォーとは?まず最初に知ってほしい治療の特徴
オールオンフォーは、上顎または下顎すべての歯を失った場合でも、4本のインプラントで固定式の人工歯列を支える治療法です。少ない本数で土台をつくれるため、身体への負担を抑えつつ、しっかり噛める環境をつくれる点が特徴です。
傾斜をつけてインプラントを埋入する独自の技術により、骨の少ない部分を避けて安定した固定を得やすく、従来のインプラントでは難しいと言われたケースにも適応できる可能性があります。
また、治療計画によっては、手術当日に仮歯を装着して「その日のうちに噛める」状態が期待できる場合もあり、生活面の負担が大きく異なる点も魅力です。
総入れ歯のように外れる心配が少なく、自然に噛める感覚を得やすいため、「食事のストレスを減らしたい」「見た目を改善したい」という方にとって非常に大きなメリットになり得ます。
・誰に“最適”なのかを歯科医が丁寧に解説
オールオンフォーは、特に以下のような方に適しているケースが多く見られます。
・総入れ歯が安定せず、外れやすさや痛みに悩んでいる方
・しっかり噛める固定式の歯を希望している方
・顎の骨が少ないと言われ、一般的なインプラントを断られた方
・見た目の改善を求めている方
ただし、どんな治療にも適応と不適応があり、全身の健康状態や骨量、生活習慣などを総合的に評価したうえで判断する必要があります。
「自分にもできるのか」「入れ歯以外の選択肢がほしい」と感じている方にとって、治療の可能性を知る第一歩としてオールオンフォーを理解することは大きな意味があります。
2. オールオンフォーが“最適な人”とは?—治療前に知っておきたい判断基準
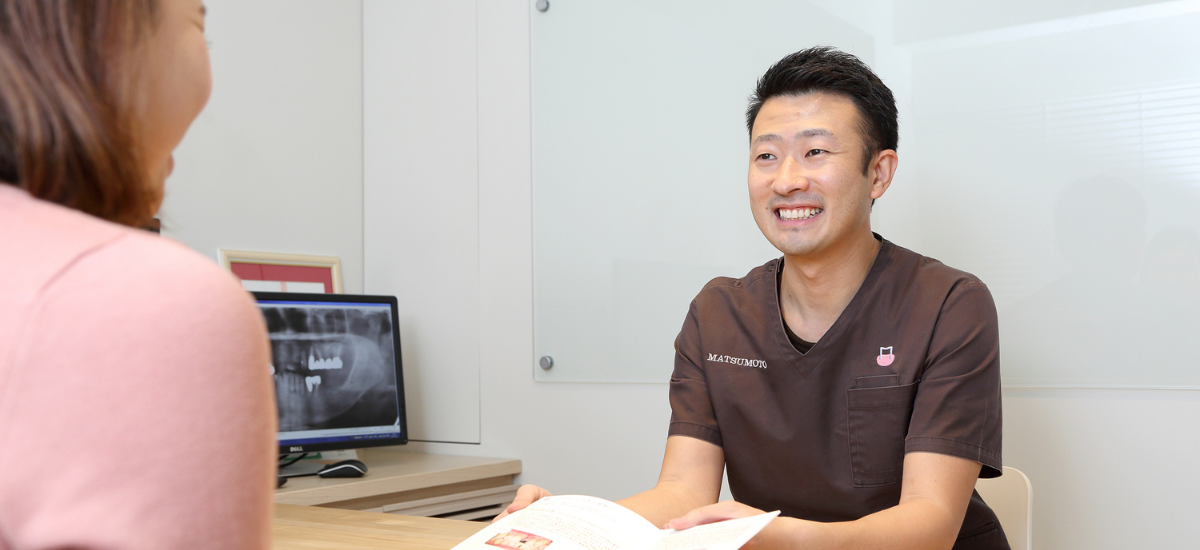
・骨量が少ない人でもできる可能性がある理由
インプラント治療では「骨の量」が大きな判断基準になります。一般的なインプラントは土台となる骨が十分にないと安定しにくく、骨造成が必要になるケースもあります。
しかし、オールオンフォーでは傾斜埋入(角度をつけてインプラントを埋め込む技術)を用いるため、骨が比較的残っている部分を選んで支えることができます。
このため、通常のインプラントでは難しいと言われた方でも、治療できる可能性が広がるケースがあります。
もちろん、すべての方に適応できるわけではありません。CTによる立体的な骨の分析が欠かせませんが、「骨が少ないから無理」と諦めていた方にとっては、新しい選択肢となり得ます。
・入れ歯生活を根本的に変えたい人に向くポイント
「入れ歯が合わない」と感じている方が検討されることが多いのも、オールオンフォーの特徴です。総入れ歯は、どうしても噛む力が弱くなり、外れやすさも避けられません。
一方でオールオンフォーは固定式であるため、ズレ・外れの不安が少なく、噛む力も大きく改善する可能性があります。
具体的には、次のようなお悩みを持つ方が向いています。
・食事中に入れ歯がズレる、痛い、外れる
・硬いものを噛むのを避けている
・入れ歯の見た目に抵抗がある
・毎日の手入れが負担に感じる
「入れ歯を使い続ける生活に限界を感じている」という方にとって、生活の質を大きく変える治療になり得ます。
・向かないケースの特徴(医療広告ガイドライン配慮)
一方で、オールオンフォーがすべての人に最適とは限りません。適応を見極めるためには、医学的な視点が不可欠です。
以下は一般的に注意が必要とされるポイントで、最終判断は診察と検査に基づいて行われます。
・重度の全身疾患があり、外科処置が難しい場合
・顎の骨の状態が著しく不安定な場合
・強い歯ぎしり・食いしばりがある場合(専用のケアが必要)
・口腔内の清掃状況が極端に悪く、感染リスクが高い場合
これはあくまで「治療前に確認すべき項目」であり、必ずしも治療できないという意味ではありません。どの治療が安全で最適かを丁寧に判断することで、長期的に安心して使える環境を整えることができます。
3. なぜ4本で支えられるのか:オールオンフォーの仕組みと専門技術

・傾斜埋入という特殊な技術
オールオンフォーが4本のインプラントで全体の人工歯列を支えられる理由のひとつが、「傾斜埋入(けいしゃまいにゅう)」と呼ばれる技術です。
通常のインプラントは骨の最も厚い部分にまっすぐ埋入しますが、オールオンフォーでは奥側のインプラントをやや斜めに角度をつけて埋入します。こうすることで、骨がしっかり残っている場所を利用しながら、長いインプラントを安定して固定できます。
斜めに埋めるというと不安に感じる方もいますが、実はこれによって骨の広い面を活用でき、強い固定力を得やすくなるという利点があります。骨造成が避けられる場合も多く、身体への負担を減らした治療計画が立てやすくなります。
・顎の骨にかかる力を分散する構造
インプラント治療では「噛む力をどのように支えるか」が非常に重要です。オールオンフォーは、前方2本+後方2本の合計4本を効率的に配置し、この4本を支点として力を均等に分散できる構造になっています。
角度をつけたインプラントが前後・左右の力を広く受け止め、噛む力のバランスがとれるよう設計されているため、少ない本数でも高い安定性を得ることが可能になります。
また、固定式の人工歯列と連結させることで、1本あたりの負担が軽減され、長期的にトラブルを抑えることにもつながります。こうした構造的な工夫が、オールオンフォーの“4本で全体を支えられる”という仕組みを支えています。
・従来の全顎インプラントとの違いをわかりやすく
従来の全顎インプラントは、上顎で6〜8本、下顎で4〜6本埋入することが一般的でした。そのため、治療期間・費用・身体への負担が大きくなる傾向があります。
一方でオールオンフォーは、必要最小限の本数で安定性を確保する設計のため、治療のステップがシンプルになりやすく、身体的負担も抑えられる可能性があります。
また、従来の方法では骨が不足している場合に骨造成が必要でしたが、オールオンフォーは傾斜埋入を活用することで骨造成を避けられるケースがあるのも大きな違いです。
こうした技術的な工夫が組み合わさることで、多くの方にとって現実的な選択肢となり、入れ歯に悩む患者様が“再び自然に噛める生活”を目指せる治療として注目されています。
4. 手術当日に“噛める歯”を装着できるメリットと注意点

・即日で歯が入る仕組み
オールオンフォーの大きな特徴のひとつが、手術当日に仮歯を装着できる「即日負荷」という治療スタイルです。通常のインプラントでは、埋入後に数カ月の治癒期間を置いてから人工歯を装着します。しかしオールオンフォーでは、角度をつけたインプラントを広い骨面で安定して固定できるため、手術直後でも仮歯を支えるだけの力が確保できるのです。
この仕組みにより、長期間歯がない状態で過ごす必要がなく、手術を受けたその日から日常生活に戻りやすいという大きなメリットがあります。「治療期間中に歯がないのは困る」「食事の予定が控えている」と不安を感じている方にとって、心理的負担を大きく減らせる要素のひとつです。
・生活がどのように変わるか
即日で仮歯が入ることで、治療当日から噛めるようになるのはもちろん、見た目の改善もすぐに実感できます。多くの患者様が「その日に笑顔で帰れた」「話しやすくなった」と変化を感じられることが多く、社会生活の不安が大きく軽減します。
さらに、仮歯の段階でも形や噛み合わせを調整できるため、生活の中で感じた違和感をフィードバックしながら、最終的な人工歯の完成度を高められる点もメリットです。
「硬いものを噛む感覚が戻ってきた」「食事が楽しくなった」という声が多く、総入れ歯で悩んでいた方にとって生活の質を大きく変えるきっかけになり得ます。
ただし、本当の意味で“しっかり噛める”のは、インプラントと骨が結合してからです。仮歯はあくまで治療の過程であり、ここでの経験を踏まえて最終的な歯の形態を整えていきます。
・手術直後の制限とリスク説明
即日で歯が入る一方、手術直後には守るべき注意点もあります。まず、インプラントが骨と結合するまでの期間(通常2〜6カ月程度)は、仮歯に過度な負担がかからないよう、硬いもの・粘着性のあるものを避ける食事制限が必要です。
また、術後数日は腫れや軽い痛みが出ることがあり、抗生剤や痛み止めの内服が処方されます。これは一般的な生体反応であり、多くの場合は数日で落ち着いていきますが、腫れのピークは術後2〜3日目になることが多いため、その点を理解して生活スケジュールを調整すると安心です。
さらに、口腔内を清潔に保つことが重要で、感染を防ぐために適切なブラッシングや殺菌作用のある洗口剤の使用が推奨される場合もあります。清掃状態が悪いとインプラント周囲炎のリスクが高まるため、術後のセルフケアは欠かせません。
これらの注意点を守ることで、即日の仮歯装着というメリットを最大限に活かしつつ、インプラントを長く安定させるための準備が整います。
5. オールオンフォーの寿命はどれくらい?—長期的な安定性を左右する要因

・一般的な寿命の目安(機能 / 補綴物)
オールオンフォーの寿命は、「インプラント本体(骨に埋まる部分)」と「人工歯(補綴物)」で異なります。
インプラント本体は、適切にケアを続ければ10年以上、場合によっては20年近く安定して使えるケースも珍しくありません。これはインプラントと骨が強固に結合しやすい特性によるものです。
一方、人工歯(補綴物)は日常的に噛む力や摩耗がかかるため、素材や使用状況によって寿命が異なり、目安としては5〜10年程度で交換や調整が必要になる場合があります。
ただし「寿命=必ず壊れる時期」ではなく、割れやすい食べ物を避ける・定期的に点検を受けるといった習慣で、長く良い状態を維持できることも多いです。
オールオンフォーは構造的に力を分散させやすいため、個々のインプラントに過剰な負担がかかりにくく、長期的な安定が期待できる点も特徴です。
・インプラント周囲炎のリスクとケアの重要性
オールオンフォーの寿命に影響する最大のリスクがインプラント周囲炎です。
これはインプラント周囲の歯ぐきや骨に炎症が起きるもので、進行すると骨が溶け、インプラントを支えられなくなる可能性があります。歯周病とよく似た病態で、日々の清掃状態が大きく関係します。
特にオールオンフォーは固定式であるため、汚れが目に見えにくい部分も存在します。だからこそ、自宅でのブラッシング方法・フロスや歯間ブラシの使い方・洗口剤の活用など、清掃方法を正しく身につけることが不可欠です。
歯科医院で定期的に専門のクリーニングを受けることで、セルフケアでは取り切れない汚れやバイオフィルムをしっかり除去できます。
インプラント周囲炎は「痛みなく進む」こともあり、自覚症状がほとんどないまま進行するケースもあります。そのため、予防と早期発見の両方が寿命を大きく左右します。
・定期メンテナンスが寿命を延ばす理由
インプラント治療の成功は、治療後のメンテナンスで大きく変わります。
定期的なメンテナンスでは以下のような項目を確認します。
・インプラント周囲の炎症や腫れのチェック
・噛み合わせのバランス調整
・補綴物(人工歯)の緩み・摩耗・破損の確認
・自宅での清掃状態の確認とアドバイス
特に噛み合わせの微妙なズレは、患者様自身では気づきにくいものです。しかし、このズレがインプラントに強い負担をかけ、寿命を縮める原因になることがあります。定期チェックで早期に調整することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、仮歯の期間にフィードバックをもとに調整を重ねることで、最終的な人工歯がより長く快適に使えるように設計できます。
「治療を受けて終わり」ではなく、継続したサポートを受けることでオールオンフォーの持つ性能を最大限に引き出し、寿命をしっかり延ばすことが可能になります。
6. オールオンフォーと総入れ歯の比較:どちらが自分に最適かを考える

・噛む力・見た目・快適性の違い
総入れ歯は、歯ぐきの粘膜部分に密着させて支える仕組みのため、どうしても噛む力が弱くなりがちです。硬いものを噛む際に痛みが出たり、力を入れづらかったりすることは珍しくありません。また、会話中や食事中に外れる心配があり、人前で自然に笑えないと感じる方もいます。
一方でオールオンフォーは、インプラントを土台として固定するため、噛む力が安定しやすく、食事の種類を大きく制限することなく楽しめる可能性があります。
さらに、人工歯は歯ぐきの質感や色調まで細かく調整できるので、見た目の自然さという点でも大きなメリットがあります。外れる心配がないことで、会話や笑顔のときの不安が少なくなり、心理的な負担が軽減される方も多いです。
・“外れない”メリットの大きさ
総入れ歯の悩みで特に多いのが「外れやすさ」です。食事中に浮いてしまったり、会話の途中でズレる感覚が気になったりと、日々のストレスにつながりやすい問題です。吸着力を高めるために調整や粘着剤を使用しても限界があり、安定性に悩み続ける方は少なくありません。
オールオンフォーは固定式のため、外れる心配がほとんどないという点が非常に大きな魅力です。
固定されていることで咀嚼のたびに安定性が変わることがなく、違和感の少ない装着感が期待できます。朝起きたときに「入れ歯を外す」「洗う」という習慣からも解放され、ケアは基本的にブラッシングを中心とした日常的な清掃で完結します。
外れない安心感は、生活の質に大きく影響します。特に人前に出る機会が多い方、よく話す職業の方では、心理的な負担が減り、日常生活の満足度が高まることが多く見られます。
・メンテナンス面の注意点
どちらの治療法にも共通して言えることですが、長く使用するためには適切なメンテナンスが欠かせません。総入れ歯の場合、歯ぐきに当たる部分の変化により、時間が経つと合わなくなるため、定期的な調整や作り替えが必要になります。
オールオンフォーの場合は「外れない」「しっかり噛める」というメリットがある一方、固定式であるがゆえに清掃が行き届きにくい部位も存在します。これを放置するとインプラント周囲炎につながるため、正しいブラッシング方法や補助清掃具の使い方を身につけることが重要です。
また、歯科医院での定期メンテナンスでは、インプラント周囲の状態だけでなく、噛み合わせの変化や補綴物の摩耗の確認も行います。定期的にチェックすることでトラブルを早期に発見し、快適な状態を長く維持することができます。
総入れ歯とオールオンフォーのどちらが最適かは、噛み合わせの状態、骨の量、生活スタイル、お口の清掃状況など多くの要素を踏まえて判断されます。患者様ごとにメリット・注意点は異なるため、丁寧に検査しながら最適な治療を選択することが大切です。
7. 費用だけで判断しないために:オールオンフォーの総額と価値

・全体の治療費がどのように決まるか
オールオンフォーの費用は「決まった一律の金額」というわけではなく、複数の要素によって変動します。診断に用いるCT撮影や模型製作、サージカルガイドの有無、当日の麻酔方法、使用するインプラントメーカー、人工歯の素材など、治療の質を左右する工程が多く含まれるためです。
また、患者様ごとに顎の骨の状態や噛み合わせの特徴が異なるため、必要な処置の内容も変わってきます。たとえば、仮歯をどのように設計するか、長期的に使える人工歯をどの素材で製作するかといった選択肢は、費用と品質の両方に関わります。
費用を比較するときには「どこまで含まれているのか」を確認することが大切です。手術費用だけでなく、仮歯・最終補綴物・術後の診察・メンテナンスなど、治療の全体像を把握したうえで判断することで、安心感のある治療計画につながります。
・長期的に見た費用対効果
治療費だけを見ると、オールオンフォーは総入れ歯よりも初期費用が高くなる傾向があります。しかし、長期的に考えると、費用対効果という点でメリットが大きいケースも少なくありません。
総入れ歯は経年的に歯ぐきの形が変化するため、調整や作り直しが必要になることがあり、結果的に継続的な費用がかかります。また、ズレや外れによるストレスが続くことで、生活の質にも影響が出る場合があります。
オールオンフォーは固定式で安定しやすく、噛む力を取り戻しやすい点が特徴です。治療後に「食事が楽しくなった」「人前で自信を持って笑えるようになった」といった心理的な満足度の向上は、お金には換えられない価値といえるでしょう。
もちろん、長く使うためにはメンテナンスが必須ですが、しっかりケアすれば10年以上の長期使用が期待でき、総入れ歯のような大幅な作り替えが頻繁に発生しにくい点も、長期的な費用対効果に貢献します。
・“安さだけ”で選ぶことのリスク
費用は誰にとっても重要なポイントですが、「安さだけ」を基準に治療を選ぶことには注意が必要です。オールオンフォーは高度な診断力と精密な技術が求められる治療であり、治療計画の質が結果に大きく影響します。
特に、使用するインプラントメーカーや人工歯の素材、術中シミュレーションやガイドの精度などは、治療の予知性を高めるうえで欠かせない要素です。費用を下げるためにこれらを簡略化してしまうと、長期的な安定性に不安が残る可能性があります。
また、治療後のフォロー体制やメンテナンスの内容が十分でない場合、トラブルが起きたときに対応がスムーズにできないリスクもあります。安心して治療を受けるためには、費用だけでなく、「どのような工程が含まれているのか」「長期的なサポートはどうなっているか」といった点を確認することが大切です。
オールオンフォーの本当の価値は、単なる“価格”ではなく、治療後に得られる機能性・快適性・見た目の自然さ、そして長期的な安心感にあります。それぞれの生活スタイルに合わせて、無理のない治療計画を立てることが、満足度の高い結果につながります。
8. 手術の流れと回復期間をリアルにイメージする

・初診〜精密検査〜シミュレーション
オールオンフォーの治療は、まず丁寧なカウンセリングから始まります。現在の悩みや生活背景、治療に求める優先順位をしっかり共有したうえで、口腔内の状態を確認します。その後、CTによる立体的な撮影を行い、骨の厚み・幅・高さ、インプラントを埋め込む角度、神経や血管の位置などを細かく分析します。
この精密検査をもとに、インプラントをどの位置に、どの角度で埋め込むかといった綿密なシミュレーションが行われます。サージカルガイドと呼ばれる補助器具を使う場合は、この段階でデータから製作され、手術の精度を高める役割を担います。
また、事前に噛み合わせの状態や表情のバランスも確認することで、治療後の人工歯が自然に見えるよう設計することができます。初診から治療計画までの段階は、成功のための“土台作り”ともいえる大切な工程です。
・手術当日の過ごし方
手術当日は、麻酔の種類によって過ごし方が変わります。局所麻酔で行う場合は意識がある状態で、静脈内鎮静法を併用するケースでは半分眠ったような状態でリラックスして受けられます。痛みを抑えながら処置が行われるため、恐怖心が強い方でも安心して臨めることが多いです。
インプラントの埋入は、シミュレーションで決めた位置に沿って進められます。4本を効率的に配置することで、骨の密度が高い部分を活かし安定した固定を得ることができます。処置後は、当日装着する仮歯を調整し、噛み合わせ・見た目を確認したうえで装着します。
手術直後は、麻酔の影響で口の周りがぼんやり感じることがありますが、多くの方はその日のうちにゆっくり歩いて帰宅できる程度の状態です。顔の腫れや違和感は数日で落ち着くことが一般的です。
・回復までの期間と食事の注意点
手術後の回復は個人差がありますが、一般的には2〜6カ月ほどの治癒期間を経てインプラントと骨がしっかり結合していきます。この期間は過度な負荷を避けることが重要で、特に最初の数週間は柔らかい食事を中心にし、硬いものや粘着性のある食品は避ける必要があります。
また、清掃面ではいつも以上に注意が必要です。インプラント周囲に汚れが溜まると感染のリスクが高まるため、歯ブラシ・歯間ブラシ・洗口剤などを組み合わせて、清潔な状態を維持することが重要です。歯科医師や歯科衛生士からの指導に従うことで、治癒期間のトラブルを防ぎやすくなります。
治癒が進み、骨との結合が安定すると最終的な人工歯の製作へ移ります。仮歯の段階で集めた噛み合わせや見た目の情報をもとに、より快適で自然な仕上がりを目指して作り上げられます。最終的な歯が入ることで、食事の幅が広がり、見た目や発音の面でもより快適に過ごせるようになります。
9. よくある疑問に答える:痛み・腫れ・持病との関係など

・手術中の痛みの実際
「インプラント手術は痛いのでは?」と不安を感じる方は少なくありません。しかし、実際には痛みを抑えるための配慮と技術がしっかり整っているため、手術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。
局所麻酔がしっかり効いている状態で行われ、必要に応じて静脈内鎮静法を併用することで、半分眠ったようなリラックスした状態で処置を受けることができます。
音や振動が気になる場合はありますが、麻酔が効いているため痛みは感じにくく、患者様の表情や緊張度に合わせて適宜声かけを行いながら進めるため、安心して臨んでいただくことができます。
・腫れのピーク
手術後の腫れは、身体の自然な反応として起こるものです。特にオールオンフォーのように複数のインプラントを埋め込む処置では、術後2〜3日目に腫れのピークを迎えることが多いです。
ただし、腫れの程度や期間には個人差があり、「ほとんど腫れなかった」と感じる方もいれば、「数日むくんだような感覚が続いた」という方まで幅があります。
氷や保冷剤で冷やしすぎると逆効果になるため、翌日以降は温めすぎないよう注意しながら、指示された痛み止めや抗生剤を服用します。ほとんどの場合、腫れは1週間前後で自然に落ち着いていきます。
内出血が出ることもありますが、多くは数日から1〜2週間で吸収され見た目も改善します。見た目の変化を心配される方には、術後の経過の目安を事前に説明することで不安が和らぎやすくなります。
・持病がある場合の注意点(ガイドライン準拠)
「持病があるけれど、オールオンフォーはできるのか?」というご質問も多くいただきます。結論としては、持病の内容や重症度によって適応が異なるため、まずは診断と医科との連携が重要になります。
代表的な例として、糖尿病が挙げられます。血糖コントロールが安定していれば治療可能なケースもありますが、コントロール不良の場合は感染リスクが高まるため注意が必要です。また、高血圧や心疾患、骨粗鬆症などがある場合も、内科医の評価や服薬内容の確認が治療計画の重要なポイントとなります。
抗凝固薬(血をサラサラにする薬)を服用している方、免疫に影響する薬を使用している方なども、減量や中止の可否を医科と相談しながら慎重に進めます。これは安全な治療のために欠かせないプロセスであり、患者様の全身状態を把握した上で無理のない治療計画を立てることが大切です。
また、持病がある方ほど術後の経過観察が重要になります。治癒のスピード、感染リスク、自宅でのセルフケアなど、注意すべきポイントを丁寧に確認していくことで、安全性と長期的な安定性をしっかり確保することができます。
10. “自分に最適か知りたい”と思ったら——後悔しないための相談の受け方

・セカンドオピニオンのすすめ
オールオンフォーは高度な治療であるため、どこで相談するかが結果に大きく影響します。もし現在の説明だけでは判断材料が少ない、あるいは不安が残るという場合には、セカンドオピニオンを受けることも良い手段です。
複数の歯科医師の意見を聞くことで、治療の方向性や提案内容が比較でき、「自分にとって本当に最適な選択」が見えやすくなります。
医療機関ごとに設備・技術・経験は異なります。検査の精度や治療計画の詳細、術後のフォロー体制など、気になる点は遠慮せず質問することで、より安心して治療に臨むことができます。セカンドオピニオンは“迷っているから行ってはいけない”ものではなく、安心して納得して治療を選ぶための大切なステップです。
・何を確認すれば安全性・寿命につながるのか
相談時に確認しておくと安心なポイントはいくつかあります。まずは、精密検査の内容が十分かどうか。CT撮影を行い、骨の量・質・神経の位置をしっかり分析しているかは、安全にインプラントを行うための基本です。また、サージカルガイドを使用する場合には、その精度や製作方法も確認しておくと良いでしょう。
次に、使用するインプラントメーカーや人工歯の素材の説明があるかどうかも重要です。長期的な安定性を考えるうえで、実績のあるメーカーや、日常生活に適した耐久性を持つ補綴物が選ばれているかは見逃せないポイントです。
さらに、術後のメンテナンス計画が明確に示されているかも、寿命を左右する大切な要素になります。定期検診の頻度、クリーニングの内容、噛み合わせの調整など、治療後のフォローがしっかり行われるかどうかは、長期的なトラブルを防ぐうえで欠かせません。
・自分に合った治療計画を立てるために
インプラント治療は患者様の生活背景や希望するライフスタイルによって、適した計画が変わります。たとえば、「早くしっかり噛めるようになりたい」「見た目を自然に整えたい」「費用を抑えたい」など、優先順位は人によって異なります。これらを事前に整理して相談すると、治療の軸がぶれずに済みます。
治療計画では、手術の段取りだけでなく、仮歯の期間をどのように過ごすか、最終的な人工歯の素材をどう選ぶか、生活習慣の改善が必要かといった点まで考慮されます。
患者様の目標と現在の状態を丁寧に照らし合わせながら計画を立てることで、「無理のない、安全で、長く使える」治療につながります。
オールオンフォーは、今の生活の困りごとを解消し、将来的に快適な毎日を取り戻すためのひとつの選択肢です。不安に感じる部分や疑問点は遠慮なく相談し、自分が納得して選べる治療を見つけることが、後悔のない道へとつながります。
『 東京審美インプラント治療ガイド:監修 松本デンタルオフィス東京 』
監修:松本デンタルオフィス東京
所在地:東京都東大和市清原4丁目10−27 M‐ONEビル 2F
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス
院長 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより