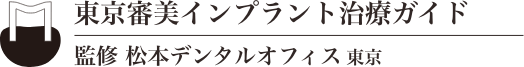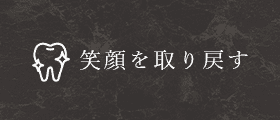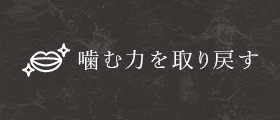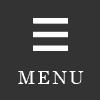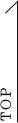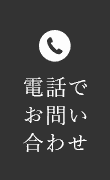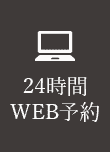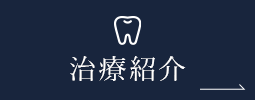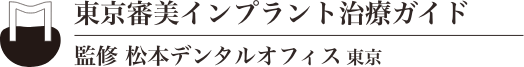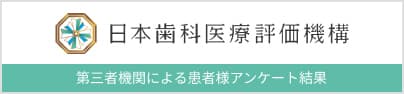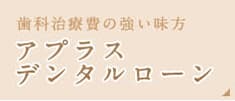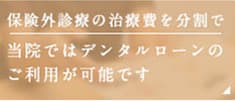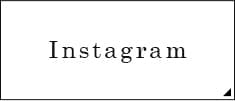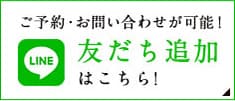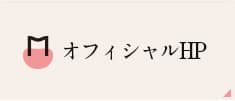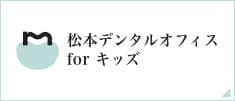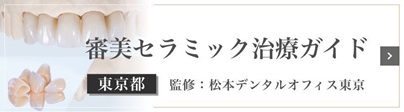1.「歯ぎしり・食いしばりがあっても、インプラントはできるの?」

・インプラントに“強い力”は大敵?基本的な考え方を知る
インプラント治療をご検討中の方の中には、「私は歯ぎしりや食いしばりがあるから、治療は無理かもしれない」と不安に思われる方も少なくありません。確かに、インプラントにとって“強い力”は大敵です。天然歯とは異なり、インプラントは歯根膜がないため、力を逃がす“しなやかさ”に欠けています。そのため、過剰な咬合力が加わると、上部構造が欠けたり、インプラント体にダメージが蓄積されてしまう可能性があるのです。
しかし、これは“だからインプラントはできない”という意味ではありません。むしろ、近年ではこうしたリスクを把握した上で、力の影響を最小限に抑えるための設計や、適切な補助装置(例:ナイトガード)を活用した治療が可能となっています。重要なのは、歯ぎしりや食いしばりの習慣を正しく診断し、治療計画に反映させることです。
・歯ぎしり・食いしばりがインプラントに及ぼす影響
歯ぎしりや食いしばりの習慣がある場合、特に注意したいのが「無意識にかかる持続的な力」です。睡眠中など意識がないときに顎に大きな力が加わり、それが日常的に繰り返されると、インプラントにかかるストレスは想像以上に大きくなります。その結果、セラミックの上部構造が割れてしまったり、周囲の骨に炎症が起きてインプラント体が緩んでしまうこともあります。
また、強い咬合力が周囲の歯にも悪影響を与え、天然歯とのバランスが崩れてしまうケースも報告されています。そのため、単にインプラントを埋入するだけでなく、周囲の噛み合わせや咬合圧の分布など、口腔全体のバランスを診る“全体最適の視点”が必要です。
・不向きというより“管理と工夫”がカギになる
「歯ぎしりがある=インプラントに向いていない」と一概に判断するのではなく、「どうすれば長く快適に使えるか」という視点で治療方針を考えることが大切です。たとえば、咬合圧を分散するために複数本のインプラントで支える設計にしたり、特定の咬合面に負荷が集中しないような補綴設計を行うなど、歯科医師の工夫によって十分に対応可能です。
さらに、インプラント埋入後のメンテナンスも極めて重要です。定期的な咬合調整やナイトガードの使用、生活習慣の見直しを継続することで、歯ぎしりや食いしばりのリスクをコントロールし、長期的な安定を図ることができます。
当院でも、歯ぎしりのある患者様に対しては、事前の噛み合わせ診断を重視し、ナイトガードの装着や生活指導を組み合わせながら、安全で安心なインプラント治療をご提供しています。「歯ぎしりがあるから…」とあきらめる前に、まずは一度、専門の歯科医師にご相談いただくことをおすすめします。
2.「なぜ歯ぎしり・食いしばりはインプラントに悪影響なのか?」

・インプラントは“天然歯のようにしなる”ことができない
インプラントは、一見すると天然歯に近い機能や見た目を持っていますが、構造的には大きな違いがあります。天然歯には「歯根膜」と呼ばれるクッションのような組織が存在し、咀嚼時に加わる力を適度に分散・吸収しています。しかし、インプラントは人工的に顎の骨に直接固定される構造で、歯根膜がありません。そのため、強い力がそのままインプラント本体や周囲の骨に伝わってしまうのです。
特に歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、無意識のうちに非常に大きな咬合力を長時間かける傾向があるため、インプラントにとっては負担が大きくなります。これは天然歯と異なり、しなやかさがないインプラントの構造にとって致命的なダメージとなり得るのです。
・噛み合わせのズレが“インプラント体”に負担をかける
歯ぎしりや食いしばりは、上下の歯が本来あるべき位置からズレた状態で強く接触することも少なくありません。こうした“偏った噛み合わせ”が続くと、特定の歯にだけ異常な力がかかり、その力が集中することで、上部構造のセラミックが割れたり、インプラント体が緩む・動揺する・最悪の場合には脱落するリスクすら生じます。
また、歯ぎしりや食いしばりが習慣化している方は、頬や舌、筋肉にも力が入りやすく、噛み合わせが変化しやすい傾向にあります。インプラントはその構造上、一度埋入した後の微調整が難しいため、こうした噛み合わせの変化に対応しきれず、不具合を起こすリスクが高まるのです。
・力のコントロールが“寿命を大きく左右”する理由
インプラントの寿命に影響する要因はいくつかありますが、「噛む力のコントロール」はその中でも極めて重要です。歯ぎしりや食いしばりがある方の場合、夜間の無意識な咬合力によって、インプラント周囲の骨にマイクロダメージが蓄積されることがあります。このダメージが蓄積すると、やがてインプラント周囲炎の引き金となり、骨吸収が進行。最終的にはインプラントの脱落につながることもあるのです。
実際に、歯ぎしりが強い患者様の中には、インプラント埋入から数年以内にトラブルが発生したケースも報告されています。これは、咬合力を十分に考慮しない設計であったり、補綴物の素材が不適切であったことが原因であることも多く、治療計画の段階で「咬合力への対応策」を講じておくことが重要です。
当院では、歯ぎしり・食いしばりがある方に対しては、必ず咬合力測定を行い、力の分散を前提とした設計・素材選びを徹底しています。さらに、術後のメンテナンスや生活指導も含めた“トータルサポート”で、インプラントの長期安定を目指しています。
「噛む力は自分ではコントロールできない」と感じる方こそ、歯科医と連携しながら治療を進めることで、安全性を確保しながらインプラント治療を実現できるのです。
3.「“壊れやすい”って本当?インプラントの耐久性と破損リスク」

・上部構造のセラミックが割れてしまうケースも
インプラント治療を検討している方の中には、「インプラントは壊れやすいのでは?」という不安を抱いている方も少なくありません。実際、インプラントそのものは非常に丈夫で、純チタンやジルコニアなどの耐久性に優れた素材で作られています。しかし、上部構造(人工歯の部分)に使われるセラミックやジルコニアクラウンは、強い衝撃や継続的な力により、欠けたり割れたりする可能性があります。
特に歯ぎしりや食いしばりの癖がある方の場合、日常的に強い力が無意識に加わることで、セラミッククラウンに微細な亀裂が入り、最終的に破折してしまうこともあります。こうしたトラブルは、見た目や機能性に影響を与えるだけでなく、再治療の必要性も出てくるため、患者様にとっては大きな負担となります。
・骨との結合部が緩む・脱落する可能性はあるのか
「インプラントが抜け落ちてしまう」という声を聞いて、不安を感じる方もいらっしゃいますが、実際には適切な治療計画とメンテナンスがなされていれば、インプラント体自体が脱落するケースは非常に稀です。しかし、強い咬合力が継続的にかかることで、インプラント体と顎の骨との結合部分(オッセオインテグレーション)が徐々にダメージを受け、骨吸収が進むことで、インプラントが不安定になり、最終的に動揺・脱落に至る可能性もゼロではありません。
さらに、歯ぎしりの力が特定のインプラント1本に集中すると、上部構造のネジが緩む・外れるというメカニカルトラブルも起こりやすくなります。これらのトラブルを未然に防ぐためには、初回の治療設計段階で“力の分散”を考慮し、複数のインプラントで負荷を受け止める配置設計や、咬合圧を考えた噛み合わせ調整が重要です。
・“強すぎる咬合力”の見極めと対処法
歯ぎしりや食いしばりが習慣化している方の咬合力は、健常な方に比べてはるかに強く、瞬間的に100kg以上の力がかかる場合もあります。この“強すぎる力”がインプラントにダイレクトにかかることで、破損・損傷のリスクが大幅に高まります。そのため、インプラント治療を行う際には、単に虫歯や歯周病の治療歴だけでなく、咬合力の測定や歯ぎしりの有無を詳細にチェックすることが必須となります。
当院では、咬合力の診断をはじめ、歯ぎしりの癖を把握するための問診・観察を通じて、リスク評価を丁寧に行っています。その上で、咬合力を緩和・分散するために、硬度の高いジルコニアを上部構造に採用したり、ナイトガードを併用した治療プランを提供したりすることで、長期安定性を追求しています。
「インプラント=壊れやすい」というイメージは、適切な診断と対策が講じられていない場合に限った話です。現在では、素材技術の進化や補綴設計の多様化によって、歯ぎしりや食いしばりがある方でも“壊れにくい”インプラント治療を実現することが可能です。
大切なのは、術前のカウンセリングでリスクをしっかりと把握し、信頼できる歯科医院で治療を受けること。「壊れないインプラント」ではなく、「壊れにくく、壊れても対応できるインプラント」を選ぶ視点が、後悔のない治療への第一歩となります。
4.「歯ぎしりする人でもインプラントができた成功事例」

・治療前の精密検査と力の分散設計がカギ
歯ぎしりや食いしばりのある方でも、適切な対策を講じればインプラント治療は十分に可能です。実際に当院で治療を受けられた50代男性のケースをご紹介しましょう。長年の歯ぎしり癖で奥歯を失い、義歯に不満を持たれていたこの患者様は、「もう自分の歯で噛む感覚を取り戻したい」という強い希望をお持ちでした。
治療を進めるにあたり、まずは精密な検査を行いました。噛み合わせの状態、顎関節の動き、咬合力の大きさを詳細に評価し、インプラントを支える骨の状態もCTで三次元的に確認。その結果、強い咬合力が一部の歯列に集中していたため、通常よりも太く安定性の高いインプラント体を選択し、複数本で噛む力を分散させるよう設計しました。
・ナイトガード併用で長期安定を実現
この患者様には、就寝時に装着するナイトガード(マウスピース)の使用も併せてご提案しました。歯ぎしりの多くは睡眠中に起こるため、無意識下での咬合圧を軽減するにはこの対策が非常に有効です。オーダーメイドで作成したナイトガードは上顎に装着するタイプで、柔軟性のある素材を使用し、違和感のない装着感を追求しました。
ナイトガードの使用とあわせて、インプラント装着後は3ヶ月おきに定期検診を実施。噛み合わせの変化やナイトガードの摩耗具合、インプラント周囲の炎症リスクを都度チェックし、問題があればすぐに対応する体制を整えています。その結果、5年経過した今も、上部構造・インプラント体ともに安定し、患者様は以前よりも快適に食事を楽しんでおられます。
・生活習慣やストレスコントロールも成功の要因に
インプラントの長期安定には、歯科的な対策だけでなく、生活習慣の改善も欠かせません。上述の患者様には、日中の食いしばりに気づくための「気づきのトレーニング」や、デスクワーク中の姿勢・呼吸法の指導も併せて行いました。さらに、ストレスが歯ぎしりの大きな要因であることをお伝えし、趣味のウォーキングや就寝前のリラックス習慣の導入を一緒に考えました。
治療に「患者様自身が積極的に関わること」が、成功の大きな要因になります。当院では、単にインプラントを“埋める”だけでなく、患者様一人ひとりの生活に寄り添いながら“インプラントとともに暮らす”ためのサポートを大切にしています。
歯ぎしりがあるからといって、インプラントをあきらめる必要はありません。適切な診断と予防策、そして信頼できる歯科医院での一貫したサポート体制があれば、十分に成功を目指すことができます。「自分には無理かもしれない」と感じている方こそ、まずは専門医にご相談ください。成功事例は、あなたにもきっと当てはまるヒントになるはずです。
5.「マウスピース(ナイトガード)はインプラントを守る強い味方」

・睡眠中の無意識な力から守る役割とは
インプラント治療を受けた患者様のなかには、歯ぎしりや食いしばりの習慣をお持ちの方が少なくありません。特に就寝中の無意識下で起こる歯ぎしりは、自覚がないまま強い力をインプラントに加えてしまうことがあり、インプラント体や上部構造にダメージを与えるリスクがあります。そんなリスクからインプラントを守るための手段として、ナイトガード(マウスピース)の活用は非常に有効です。
ナイトガードとは、睡眠中に装着することで上下の歯の接触を防ぎ、インプラントや天然歯を保護する装置のことです。硬めのアクリル樹脂や、適度に柔軟性のある素材で作られており、強い咬合力を分散させる役割を果たします。インプラントは天然歯と違い、歯根膜のような“クッション機能”がないため、外からの衝撃を直接受けやすくなっています。そうした力の負担を和らげるためにも、ナイトガードは重要なパートナーとなります。
・オーダーメイド設計の重要性
市販のマウスピースも存在しますが、インプラント治療を受けた方には、歯科医院でのオーダーメイド設計を強くおすすめします。オーダーメイドのナイトガードは、咬合関係や顎の動き、インプラントの位置を細かく計算して設計されており、適切な厚みや硬さ、装着感が確保されます。
また、患者様ごとの歯列の形状やかみ合わせの特徴に合わせて作製するため、違和感が少なく、継続的に使用しやすいという利点もあります。装着感が悪いと、せっかく作っても使われなくなってしまうことがあります。快適に装着でき、インプラント保護という役割を十分に果たすナイトガードを作るには、精密な型取りと噛み合わせのチェックが欠かせません。
さらに、インプラントの本数が多い場合や、上下のかみ合わせに大きなズレがある場合などには、ナイトガードの形状に工夫が必要になることもあります。当院では、装着後の使用感や耐久性についても確認し、必要に応じて微調整を行っています。
・“長く持たせる”ための地道な予防策
インプラントは決して「入れたら終わり」の治療ではありません。むしろ、治療後のメンテナンスや生活習慣の改善こそが、インプラントの寿命を大きく左右します。その中でも、ナイトガードの使用はもっとも手軽で効果的な予防策の一つです。歯ぎしりや食いしばりによる摩耗や衝撃からインプラントを守るだけでなく、天然歯や顎関節への負担も軽減できます。
実際、ナイトガードを継続的に使用されている患者様では、上部構造の破損やインプラント周囲炎などのトラブルが起こる頻度が明らかに低くなる傾向があります。特に夜間の無意識下では、日中には考えられないほど強い力が加わることもあるため、「壊れてから対処」ではなく、「壊れる前に予防する」という考え方が重要です。
当院では、インプラント治療後のフォローアップとして、ナイトガードの使用を含めた生活指導を丁寧に行っています。「長持ちするインプラント」を実現するには、患者様ご自身の協力が不可欠です。少しの習慣が、大きな結果につながります。治療後も安心して快適な生活を送っていただけるよう、当院は全力でサポートいたします。
6.「“歯ぎしりを治せば大丈夫”は間違い?根本原因への理解」

・ストレス・噛み合わせ・生活習慣が複雑に絡む
「歯ぎしりを治せば、インプラントも問題なく長持ちするはず」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし現実には、歯ぎしりという症状は単独で存在しているわけではなく、いくつもの要因が絡み合って発生しているため、単純に“治す”というより、“正しく理解し、コントロールしていく”という視点が重要です。
代表的な原因としては、まずストレスが挙げられます。精神的な緊張状態が続くと、無意識に歯を強く噛みしめてしまうことがあります。また、日中は意識していても、就寝中は自律神経の働きにより制御が難しくなり、歯ぎしりや食いしばりが発生しやすくなります。これが、インプラントに強い力を加えることにつながり、寿命を縮めるリスクを高めてしまいます。
さらに、かみ合わせの不調和も大きな原因のひとつです。上下の歯の当たり方にズレがあると、それを無意識に補正しようとして咬合力が一部に集中しやすくなり、歯ぎしりの誘因になります。加えて、生活習慣(例:姿勢、スマホの多用、睡眠不足など)も関与していることがあり、こうした要因が複雑に絡み合うことで、歯ぎしりが慢性化していくのです。
・完全に治すのは難しいからこそ“うまく付き合う”が正解
歯ぎしりに対して「治療=完全になくなる」というイメージを持たれている方も多いのですが、実際は完治が難しいケースがほとんどです。これは、原因が多因子であること、そして無意識下での習癖であるため、再発や慢性化しやすいという特徴があるからです。
だからこそ、“治そうとするより、うまく付き合う”という発想が大切です。具体的には、日中の意識づけ、ナイトガードの使用、咬合調整、ストレスマネジメント、姿勢改善など、多方面からアプローチを行い、インプラントや他の歯に悪影響を及ぼさないように“力のコントロール”をしていくことが有効です。
当院でも、患者様のライフスタイルや精神的背景を含めてカウンセリングを行い、単なる“力の問題”としてではなく、習癖・心身のバランスとして歯ぎしりと向き合っています。生活習慣の改善や、リラクゼーションの導入なども提案し、患者様の現実的な状況に寄り添ったケアを心がけています。
・歯科医と連携した“総合的アプローチ”が必要
歯ぎしりへの対処として最も効果的なのは、歯科医との継続的な連携です。インプラント治療を成功させるには、手術技術だけでなく、その後の生活全体を見据えたサポート体制が不可欠です。たとえば、ナイトガードを用いた力の分散、咬合調整による過負荷の軽減、ストレスカウンセリングなど、総合的な視点で患者様の口腔環境を整えていきます。
歯ぎしりが疑われる方には、まず咬合力の測定や、睡眠時の習癖の確認を行い、そのうえで最適な対応を提案いたします。インプラントを安全に、そして長く使っていただくためには、治療後の環境整備こそが最も重要なステップです。
当院では「歯ぎしりがあるからインプラントは無理」と一律に判断するのではなく、患者様の状態を細かく見極めたうえで、“可能性を高める方法”を一緒に探すスタンスを大切にしています。どんな状態の方でも、適切な管理があれば、インプラント治療の成功は十分に目指せます。ご不安な方は、ぜひ一度、無料カウンセリングでご相談ください。
7.「かみ合わせの調整でリスクを軽減する方法とは?」

・インプラント治療時にかみ合わせの分析が必須な理由
インプラント治療を成功に導くうえで、単に人工歯を入れるだけでは不十分です。特に歯ぎしりや食いしばりの癖がある方にとっては、かみ合わせの調整が欠かせないステップになります。天然歯と異なり、インプラントは歯根膜が存在せず「しなり」がありません。そのため、噛んだときの力を吸収できず、ダイレクトに力を受け止めてしまう構造となっています。
このような特性があるため、わずかなかみ合わせのズレでも一部に負荷が集中してしまい、インプラント体や上部構造に過剰なストレスがかかる危険性があるのです。その結果、インプラントの脱落や、上部のセラミックの破損、顎関節の不調などが生じるリスクがあります。
当院では治療計画の段階から咬合力の分析やバイト検査(かみ合わせの高さ・位置の計測)を実施し、力のバランスに配慮したインプラント設計を行っています。こうした細かな配慮こそが、長く機能するインプラント治療の土台となります。
・高さ・角度・咬合圧のバランス調整の重要性
かみ合わせの調整には、見た目だけでなく噛むときの高さ・角度・咬合圧のコントロールが必要です。とくに、歯ぎしり・食いしばりの癖がある方は無意識に強い力が加わるため、どこにどれだけの力がかかっているかを精密に測定し、力の分散設計を行わなければなりません。
たとえば、奥歯でインプラントを入れる際、わずかな噛み合わせの高さの違いでも、全体の咬合バランスが崩れやすくなります。また、前歯部への力が偏れば、顎関節に負担がかかる恐れも出てきます。これを防ぐには、噛むときの角度・接触点・咬合圧を可視化し、点でなく面で力を分散させる調整が必要です。
当院では、マイクロスコープや咬合器、デジタルシステムを用いた細やかな調整を行っており、「しっかり噛めるけれど、壊れにくい」状態を目指しています。さらに、治療後も咬合チェックを定期的に行い、生活習慣の変化に応じた微調整も継続してサポートいたします。
・微調整で“壊れない・長持ちする”を目指す
かみ合わせは、日々の生活の中で微妙に変化していきます。歯のすり減り、骨の変化、姿勢の癖、さらにはストレスによる筋緊張など、様々な要因が複雑に影響し合っています。そのため、インプラント治療後も「入れたら終わり」ではなく、定期的なチェックと微調整を行うことで、インプラントの長期安定につながるのです。
特に歯ぎしりや食いしばりがある方は、時間帯や状況によって咬合力が大きく変動するため、ナイトガードの活用や生活指導とあわせた包括的な管理が欠かせません。実際に、かみ合わせの微調整を怠ったことで、せっかく埋入したインプラントが数年以内にトラブルを起こしてしまうケースもあります。
当院では、「一人ひとりに合った咬合バランス」を丁寧に見極めることで、過度な力の集中を避け、インプラントの寿命を延ばす取り組みを徹底しています。治療後も咬合チェックや調整を無料で実施しており、患者様にとって“壊れない・長持ちする”安心のインプラントライフをサポートしています。
「自分の噛み合わせに自信がない」「噛むときに違和感がある」と感じている方は、ぜひ一度、咬合診断を受けてみてください。あなたの歯ぎしり・食いしばりに対して、今できる最善の方法をご提案させていただきます。
8.「歯ぎしりをする人に適したインプラント素材の選び方」

・ジルコニア vs チタン、どちらが適している?
インプラント治療に使われる素材には、大きく分けて「チタン」と「ジルコニア」の2種類があります。どちらも高い生体親和性を持ち、体内で拒絶反応を起こしにくいという共通点がありますが、歯ぎしりや食いしばりがある方にとっては、その違いがインプラントの耐久性や安定性に大きく関わってきます。
チタンは、長年にわたりインプラントの主流素材として用いられてきました。非常に軽量で強度が高く、骨としっかり結合する性質があるため、あらゆる症例に適応可能です。ただし、強すぎる咬合力が加わると、骨との結合部に過度な力が集中してしまうリスクがあります。
一方で、ジルコニアはセラミック素材で、金属を使用していないため、金属アレルギーの心配がないという利点があります。見た目も自然で、前歯部の審美性を重視する方に好まれる傾向があります。ただし、素材としては硬くてもろい面があるため、強い歯ぎしりには注意が必要です。
・上部構造の強度と柔軟性のバランスを考える
インプラントの構造は、大きく分けて「人工歯根(フィクスチャー)」と「上部構造(被せ物)」で構成されています。このうち、特に歯ぎしりのある方にとって重要なのが、上部構造の素材選びです。
一般的に、上部構造にはセラミック、ジルコニア、メタルボンドなどが使われます。なかでもジルコニアは、非常に高い耐久性を持ちますが、硬すぎるために反対側の歯や周囲の歯にダメージを与えるケースも報告されています。食いしばりが強い方の場合、セラミックの代わりにやや柔軟性のあるハイブリッドレジンやメタルフレームを採用することで、衝撃を緩和しやすくなります。
また、インプラントを複数本入れる場合には、連結式にして力の分散を図る設計にすることで、1本あたりの負担を軽減する工夫もできます。咬合力が強い方には、素材の組み合わせや連結構造を含めたカスタム設計が非常に有効です。
・素材の違いで“負荷のかかり方”も変わる
歯ぎしり・食いしばりのある方にとって、素材選びのポイントは「強度」だけではなく、「負荷の分散性」「衝撃吸収性」「対向歯へのやさしさ」も考慮すべき要素です。例えば、硬度の高い素材は耐久性には優れますが、噛み合わせた際の衝撃が相手の歯に直接伝わり、歯のすり減りや破折の原因になることもあります。
当院では、素材の特性を患者様ごとに分析し、「かみ合わせの状態」「生活習慣」「咬合力の分布」などを総合的に判断して、最適な素材と構造を提案しています。特に咬合力が強い方には、ジルコニアを選ぶ際にも厚みの調整や角の丸みをつけるなどの工夫を加え、力の逃げ場を設けるよう設計しています。
また、素材だけに頼るのではなく、ナイトガードの併用やメンテナンス体制の整備も含めて、トータルでインプラントを長持ちさせるアプローチを行っております。素材選びは、あくまでも成功の「一部」であり、「長く安定して使える環境づくり」が何より大切なのです。
歯ぎしりがあるからといって、インプラントを諦める必要はありません。あなたの口腔状態と噛み癖に最適化されたオーダーメイドの素材選定で、長く使える安心のインプラント治療をご提案いたします。まずは一度、丁寧なカウンセリングで現在の状態を一緒に見ていきましょう。
9.「当院の“歯ぎしりがある方”へのインプラント治療方針」
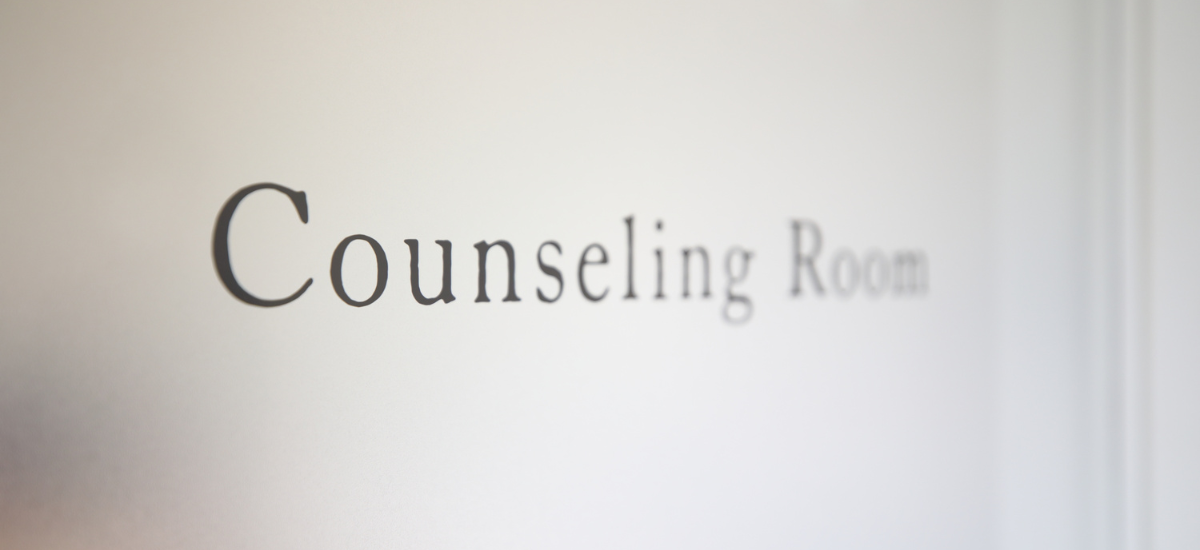
・力の診断・噛み合わせ調整・ナイトガード設計まで一貫対応
当院では、歯ぎしりや食いしばりのある患者様にも安心してインプラント治療を受けていただけるよう、専用の診断プログラムと治療設計を用意しています。まずは咬合力の測定や歯列のバランス分析を通して、現在のお口の状態を正確に把握。そのうえで、インプラントにかかる力を最小限に抑える設計を行います。
たとえば、歯ぎしりの傾向が強い場合には、インプラント体の角度・埋入深度・連結方法を調整し、過度な負荷が集中しないよう設計します。さらに、ナイトガードの併用によって、夜間の無意識な咬合圧からインプラントを守ることが可能です。これらを一貫して院内で対応できる体制を整えているため、治療の一貫性・精度も高めることができます。
・メンテナンスと生活指導の連携体制
インプラント治療は「入れて終わり」ではありません。特に歯ぎしり・食いしばりのある方にとっては、術後の管理が長期安定に直結します。当院では、定期的なかみ合わせのチェックや、上部構造にわずかなひずみが出た場合の早期調整など、メンテナンスの質にもこだわっています。
さらに、生活習慣の見直しも非常に重要です。歯ぎしりの原因には、ストレスや睡眠の質、姿勢、咀嚼の偏りなどさまざまな要因が関係しています。当院では、歯科衛生士・医師・カウンセラーが連携し、患者様の生活背景を丁寧にヒアリングしながら、再発を防ぐためのアドバイスやサポートを行っています。
歯ぎしりの癖がある方には、インプラント治療だけでなく、お口全体の健康づくりをサポートする体制が不可欠です。当院では、トータルケアを視野に入れた診療を行っています。
・“無理にすすめない・向き合う”スタンスで安心の診療
歯ぎしりがある患者様に対して、「すぐにインプラントをしましょう」と無理に治療を勧めることはありません。当院では、患者様ご自身がインプラントのメリット・デメリットを理解し、納得された上で治療を進めることを最も大切にしています。
「歯ぎしりがあるからインプラントは無理」と自己判断してしまう方も少なくありませんが、適切な診断と管理体制が整えば、インプラント治療は十分に可能です。私たちは、まず患者様の不安に耳を傾け、そのうえで無理のない計画を一緒に考えていくことを大切にしています。
万が一、歯ぎしりの影響が大きくリスクが高いと判断される場合は、代替治療のご提案も可能です。インプラントに限らず、患者様にとって最適な治療を提供するのが当院のポリシーです。
歯ぎしりのある方でも、適切な診断と工夫を重ねることで、インプラント治療を安全かつ長期的に成功させることが可能です。まずは「自分でもできるのかな?」という疑問から、当院の無料相談で一緒に解決してみませんか?
10.「歯ぎしりがあっても、まずは気軽にご相談ください」

・インプラントが無理だと決めつけないで
「歯ぎしりがあるから、自分はインプラントは無理」と思い込んでいませんか?確かに、歯ぎしりや食いしばりが強い方にとって、インプラントは注意が必要な治療です。しかし、だからといって治療そのものが不可能になるわけではありません。大切なのは、その癖を前提とした適切な診断と治療計画を立てること。専門知識をもった歯科医師が対応すれば、歯ぎしりがあってもインプラントを長く安定して使い続けることは十分に可能です。
むしろ、奥歯のインプラントがないまま歯ぎしりが続くことによって、他の天然歯や噛み合わせにさらなる負担をかけてしまう可能性もあります。だからこそ、「インプラント=向いていない」と早合点するのではなく、「自分にはどんな選択肢があるのか?」を専門医と一緒に見極めることが大切なのです。
・専門医が“リスクと可能性”を丁寧にご説明
当院では、初回カウンセリングから丁寧なヒアリングと検査を行い、患者様の咬合力や歯ぎしりの傾向を把握したうえで、適した治療の方向性をご提案します。治療ありきではなく、あくまで患者様の生活背景やお悩みに寄り添った対話を大切にしています。
「夜中に無意識に噛んでしまう」「歯ぎしりのせいで詰め物がよく割れる」といった症状がある場合は、必要に応じてかみ合わせの専門的な検査を行います。また、インプラント以外の治療法との比較も交えて、メリット・デメリットをわかりやすくご説明いたします。
このように、当院では“押しつけるのではなく、一緒に考える”スタンスで診療にあたっています。無理に治療をすすめることはありませんので、「話だけ聞いてみたい」「不安なことを相談したい」といった軽いお気持ちでも、遠慮なくお越しください。
・「あきらめない治療」の第一歩はカウンセリングから
歯ぎしりや食いしばりは、現代人の多くが抱える癖のひとつです。忙しい日々やストレス、食習慣の乱れ、睡眠の質の低下など、さまざまな要因が絡み合って無意識のうちに悪化していきます。だからこそ、「歯ぎしりがあるから治療をあきらめる」のではなく、「どうすればうまく向き合いながらインプラントと付き合っていけるか」を一緒に考えていく姿勢が大切です。
当院では、歯ぎしりのある方に向けたインプラント治療のノウハウを多数蓄積しており、力の分散設計やナイトガードの活用、生活習慣指導までをトータルでサポートできる体制を整えています。
歯の健康は、人生の質を大きく左右するものです。「もう少し噛めるようになりたい」「好きなものを安心して食べたい」という思いを、ぜひ私たちにお聞かせください。歯ぎしりがあっても、きっとあなたにとって最適な方法が見つかります。
まずは無料相談から、お気軽にどうぞ。あなたの“あきらめない選択”を、私たちが全力でサポートいたします。
『 東京審美インプラント治療ガイド:監修 松本デンタルオフィス東京 』
監修:松本デンタルオフィス東京
所在地:東京都東大和市清原4丁目10−27 M‐ONEビル 2F
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス
院長 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより